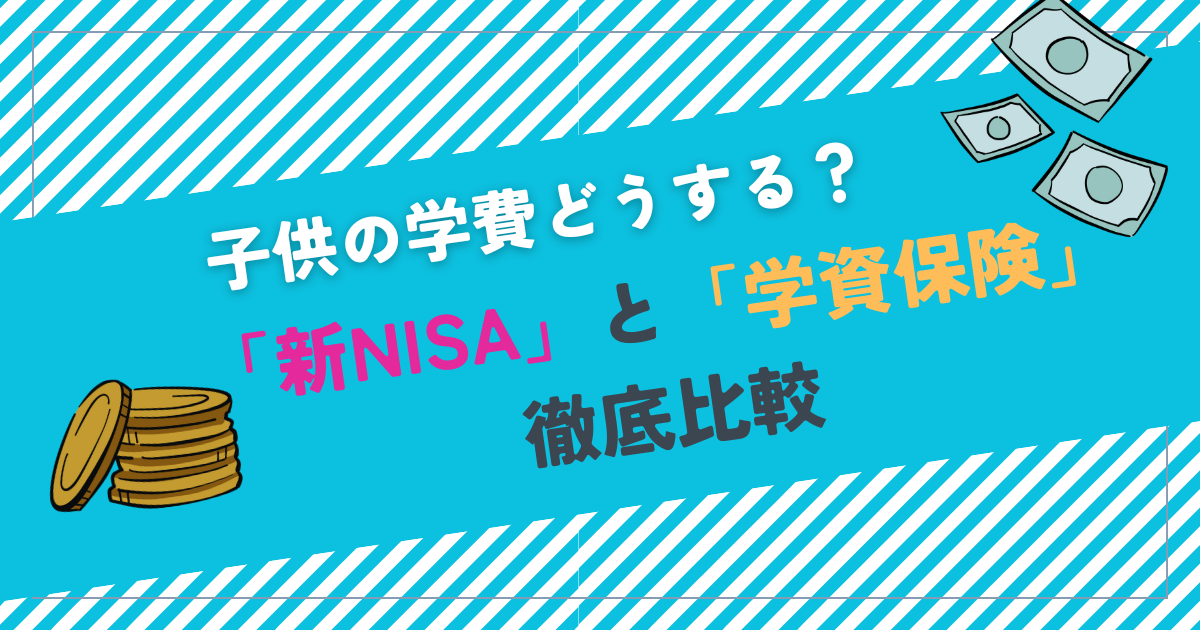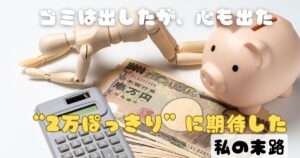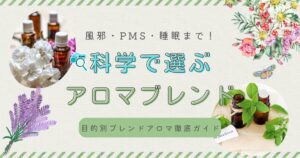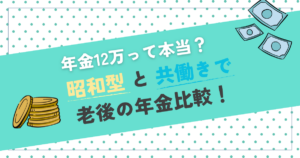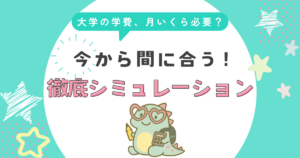この記事では、こんな疑問にお答えします
・学資保険と新NISA、それぞれの特徴や違いは?
・ジュニアNISAが終わった今、どんな選択肢があるの?
・「どんな人にどちらが向いているか?」の判断ポイントは
将来の教育費、考えなきゃ…と思いつつも、
「まだ先だし大丈夫かな?」と後回しにしがちですよね。
でも実際には、幼稚園や保育園の準備、小学校の入学に向けて、ちょこちょこと出費が増えてきて、「これからいくらかかるんだろう…?」と不安になること、ありませんか?
そんな中で最近よく聞くのが、
「ジュニアNISAが終わるらしい」
「新しいNISAってどうなの?」
「やっぱり学資保険が無難?」
…という声。
 つるぴよ
つるぴよ資産運用ってちょっとハードルが高そうだけど…
でも、せっかくなら少しでもお得に貯めたい!
そんなママ・パパのために、本記事では、教育資金を「学資保険」と「新NISA」で準備する場合の違いやメリット・デメリットを、できるだけやさしく・わかりやすくまとめています。
難しい制度の話もなるべくかみ砕いてお伝えするので、ぜひリラックスして読んでみてくださいね。
2. 教育資金って、どれくらいかかるの?
「教育資金を準備しておこう」と言っても、具体的にいくらぐらい必要なのかって、なかなかピンとこないですよね。まずは、文部科学省などの公的な調査をもとに、幼稚園から大学卒業までにかかる費用の目安をざっくり見てみましょう。
● オール公立の場合(すべて公立の学校に通った場合)
| 教育段階 | 教育費の目安(総額) |
|---|---|
| 幼稚園(3年) | 約69万円 |
| 小学校(6年) | 約193万円 |
| 中学校(3年) | 約146万円 |
| 高校(3年) | 約137万円 |
| 大学(4年・国公立) | 約523万円 |
| 合計 | 約820万円 |
※この金額は、授業料や入学金のほか、給食費・学用品・通学費・塾代などを含めた「すべての教育費」の合計です。
地域差や家庭によって前後することがあります。
出典:文部科学省「令和3年度 子どもの学習費調査」
● 幼稚園〜高校まで私立、大学は私立(理系)(※さらに一人暮らし想定)
● 幼稚園〜高校まで私立、大学は私立理系(※一人暮らし想定)の場合
| 教育段階 | 教育費の目安(総額) |
|---|---|
| 幼稚園(3年) | 約158万円 |
| 小学校(6年) | 約958万円 |
| 中学校(3年) | 約422万円 |
| 高校(3年) | 約291万円 |
| 大学(4年・私立理系・自宅外) | 約1,460万円 |
| 合計 | 約3,290万円(!) |
※大学進学時に親元を離れて一人暮らしを始めたケースをモデルにしています。生活費(家賃・食費など)も含んだ金額で、進学先が理系の場合は文系よりも授業料が高いため、やや高めの試算になります。
※この金額は、授業料や入学金のほか、給食費・学用品・通学費・塾代などを含めた「すべての教育費」の合計です。
地域差や家庭によって前後することがあります。
出典:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果(令和4年度)」/文部科学省「私立大学等の令和4年度入学者に係る学生納付金調査」など
このように、すべて公立でも約800万円以上、進路によっては3,000万円超えも珍しくないのが今の教育費事情なんです。
特に最近は物価も上がっているので、「今の相場」がそのまま未来に通用するとは限りません。インフレ(物の値段が上がること)によって、将来の教育費がさらに膨らむ可能性も十分あります。
「まだ小さいし大丈夫」は、実はチャンス!
お子さんが0歳〜未就学児の今こそ、じつは教育資金の準備を始める一番のチャンスなんです。
なぜなら、
- 時間をかけてコツコツ準備できる
- 積立や運用で「お金に働いてもらう」ことができる
- 大学入学(約18年後)までの長期目線の計画が立てやすい
から。しかも、早めにスタートすれば少額でも十分な準備が可能です。
「何から始めればいいのか分からない…」という方も大丈夫。
次の章では、最近よく話題にあがる「ジュニアNISA」や「新NISA」の制度について、やさしく解説していきますね。
3. ジュニアNISAは終了。今どうなっている?
「子どもの教育資金を増やす手段」として以前よく話題になっていたジュニアNISA。
でも最近「ジュニアNISAはもう使えないらしい」と聞いて、「えっ、結局どうなったの?」とモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか?
ここでは、ジュニアNISAがどうして終わったのか・今どうなっているのかをわかりやすく解説します。
● ジュニアNISAって、どんな制度だったの?
まず、ジュニアNISAとは…
0〜17歳の未成年のために親などが資産運用できる非課税制度のこと。
- 年間80万円までの投資枠
- 運用益が最長5年間「非課税」
- 原則18歳まで引き出せない(※だった)
という特徴があり、「子どもの教育資金を投資で育てたい!」という家庭に注目されていました。
● ジュニアNISAは2023年末で終了
2023年をもって、ジュニアNISAの新規利用は終了となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度終了時期 | 2023年12月31日で非課税投資が終了 |
| 新規口座開設 | 2023年9月末で受付終了 |
| 新規投資 | 2023年中まで(終了済み) |
| その後の運用 | 既に購入済みの商品は引き続き非課税で保有可能 |
| 払い出し | 以前は18歳まで不可 → 今はいつでも引き出せる |
● 今はどうなっているの?
2024年以降は、ジュニアNISAの新たな投資はできませんが、すでに保有している商品はそのまま非課税で保有・運用可能です。
さらに大きな変更点として、
2024年からは、18歳未満でもいつでも引き出しOKに!
もともとは「子どもが18歳になるまで引き出せない(原則)」というルールがありましたが、それが撤廃されて、自由に出金できるようになりました。
「万が一のときでも引き出せないなんて不便…」という声も多かったので、これはかなり大きな改正です。
● 新NISAに移せるの?
これはちょっと注意が必要なポイントですが、
ジュニアNISAから、新NISAへの“移し替え”はできません。
保有している商品はそのまま持ち続けるか、売却して現金化する形になります。
● 結局、ジュニアNISA終了ってどういうこと?
簡単に言うと、
- 新規では使えない制度になった
- 既存の口座は持ち続けられる(非課税で)
- ただし、今後の追加投資や運用には使えない
- 18歳未満でも引き出し自由になった(これはありがたい!)
- でも、新NISAへそのままスライドはできない
という状態です。
● じゃあこれからはどうするの?
ジュニアNISAが終わった今、子どもの教育資金を運用して増やしたいなら、
「親名義で新NISAを使う」
または、「学資保険でコツコツ貯める」
この2択(もしくは両方)をどう使い分けるかが、大事なポイントになります。
次の章では、いよいよ「新NISAってどんな制度?子どもに使えるの?」というところを、わかりやすく解説していきますね。
4. 新NISAってどんな制度?子どものために使えるの?
「ジュニアNISAは終わっちゃったけど、新しいNISA制度が始まったって聞いたよ…?」
「でもそれって、子どものためにも使えるの?」
そんな疑問を持っている方も多いと思います。
この章では、2024年にスタートした【新NISA】のしくみと、子どもの教育資金にどう活用できるかをやさしく解説していきますね!
● 新NISAって、どんな制度?
新NISAは、2024年からスタートした「恒久化&拡充」された投資の非課税制度です。
かんたんに言うと…
“長く・たくさん・自由に” 投資ができるお得な制度に生まれ変わった!
という感じです。
| 新NISAの主な特徴 | 内容 |
|---|---|
| 利用できる人 | 18歳以上の日本在住者 |
| 年間の非課税投資枠 | 最大 360万円(積立枠120万+成長投資枠240万) |
| 生涯の非課税投資枠 | 最大 1,800万円(うち成長投資枠は上限1,200万円) |
| 非課税期間 | 無期限(いつまで持っていてもOK) |
| 使える投資商品 | 株、ETF、投資信託など(枠により制限あり) |
| 使い道 | 教育費、老後資金、住宅費など自由にOK |
● 子ども本人は使えるの?
ここはちょっとややこしいのですが…
新NISAは「18歳以上」からしか使えません。
つまり、未成年の子ども名義では新NISA口座は作れないんです。
(※これはジュニアNISAが終了した影響で、現在は子ども専用のNISA制度が存在しない状態)
● じゃあ、子どもには使えない…?
いえいえ、親の名義で新NISAを活用することで、教育資金をしっかり準備することは可能です!
● 親名義で「教育費用」を新NISAで準備する方法
親が新NISA口座で投資をして、その資金を将来、子どもの進学に使う。
これなら制度上まったく問題ありません!
たとえばこんなイメージ:
今からコツコツ積立 → 18歳ごろに取り崩して学費に充てる
という形ですね。
● メリットは?
新NISAで教育資金を準備するメリットはたくさん!
- 運用益が非課税(税金がかからないってすごいこと!)
- 積立しながら資産が育つ(銀行に預けるより断然お得)
- インフレ対策にもなる(物価が上がってもお金の価値を守れる)
- 用途も引き出しも自由(教育以外にも使える柔軟性)
しかも、投資信託なら月100円から始められるから、「ちょっと試してみようかな?」という方でも安心です。
● デメリットは?
もちろん、注意点もあります。
- 元本保証はなし(投資なので、損する可能性もゼロではない)
- 自分で商品を選ぶ必要がある(とはいえ初心者向け商品もあるよ)
- 途中で運用を止めてしまうと効果が薄くなる(コツコツが大事)
特に教育資金は「使うタイミングが決まっている」お金なので、
お子さんが中学〜高校生になる頃には、リスクの低い商品に切り替えるなどの対策が大切です。
● 「教育資金にNISA」はアリなの?
結論から言うと…
「長期でコツコツ積み立てできるなら、教育資金にも新NISAはアリ!」
というのが、今の定番の考え方です。
「確実に決まった額を用意したい」なら学資保険、
「なるべく効率よくお金を増やしたい」なら新NISA、
…というように、それぞれに得意分野があるんですね。
次の章では、いよいよ「じゃあ、学資保険って実際どうなの?」というところを詳しく見ていきます!
5. 学資保険ってどんなもの?メリット・デメリットまとめ
ここまで「投資で教育資金を準備する方法(新NISA)」について見てきましたが、「やっぱり投資はちょっと不安…」という方もいらっしゃると思います。
そんな方に今も根強い人気があるのが、学資保険です。
ここでは、学資保険のしくみや特徴、そして新NISAと比べたときのメリット・デメリットについて、わかりやすく整理していきますね。
● 学資保険ってどういうもの?
教育資金専用の“貯金+保険”のような商品です。
親が毎月決まった保険料を払い込み、子どもの進学時期(高校・大学など)にお祝い金や満期金という形で教育資金が受け取れるしくみ。
また、親に万が一のことがあった場合には、それ以降の保険料の支払いが免除され、予定通りに学資金が受け取れる保障機能もあります。
● 学資保険の特徴まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料の支払い期間 | 例:10年払、18歳まで払など選べる |
| 満期金の受け取り時期 | 高校・大学入学時、または一括受取など |
| 返戻率(増える率) | 約105~110%程度が一般的(契約内容による) |
| 万一のとき | 親が亡くなった場合などは保険料免除+満期金支給 |
| 税制優遇 | 保険料が「生命保険料控除」の対象になる(年末調整・確定申告でお得) |
● メリットは?
1. 元本保証がある安心感
満期まで保険料を払い続ければ、確実に学資金を受け取れるのが大きな安心ポイントです。
「絶対に減らしたくない」「確実に貯めたい」タイプのママにはぴったり!
2. 親に万一があっても教育資金が守られる
もし契約者(親)に不幸があった場合でも、以降の保険料は払わなくてOK。それでも満額の学資金が受け取れるのは、保険ならではのメリットです。
3. 節税効果がある
保険料が「生命保険料控除」の対象になるため、毎年の税金(所得税・住民税)を軽減できる可能性があります。少しでも節約したい家庭にはうれしいポイント。
4. 使途がはっきりしているので、流用しにくい
お祝い金や満期金を教育目的で受け取る前提なので、「つい貯金を使っちゃった…」が起こりにくい。強制的に貯められる仕組みとも言えます。
● デメリットは?
1. リターンは控えめ
最近の学資保険は、返戻率が105〜110%程度とやや低めです。
「たくさん増やしたい!」という目的にはやや物足りなさも…。
例えば、返戻率が105%の保険に加入して、18年間で合計100万円の保険料を支払った場合
→ 満期時に戻ってくるのは 105万円(+5万円のリターン)ということになります。
同じく返戻率が110%なら、受け取れるのは 110万円(+10万円)になります。
2. 途中でやめると損をする可能性がある
解約すると、返ってくるお金が支払った保険料よりも少なくなることがあります。
特に加入してすぐや、数年以内にやめる場合は要注意!
3. 資金の使い道・タイミングが固定される
契約時に受け取り時期が決まっているので、たとえば「大学じゃなくて留学費に回したい」「浪人した」など予定外の事態に柔軟に対応しにくいことも。
4. インフレに弱い
将来、物価がどんどん上がった場合に、固定された満期金では教育費が足りなくなる可能性もあります。
● イメージしやすく!メリット・デメリット早見表
| 特徴 | 学資保険 |
|---|---|
| 元本保証 | ◎(満期まで払えば確実) |
| 増える金額 | △(返戻率105~110%程度) |
| 保障(親の万一) | ◎(払込免除+満額支給) |
| 節税 | ○(生命保険料控除あり) |
| 流動性 | △(途中解約で元本割れの可能性あり) |
| インフレへの耐性 | △(将来の物価上昇には対応しにくい) |
● こんな人におすすめ!
- 投資はちょっと不安…というママ・パパ
- 教育資金は絶対に減らしたくない!という方
- 家計にメリハリをつけて「計画的に貯めたい」方
- 万一の備え(保険)も一緒に考えたい方
次の章では、いよいよこの「新NISA」と「学資保険」をズバッと比較!
それぞれのメリット・デメリットを一望できる表や、「どちらが向いているか?」も紹介しますよ〜!
6. 新NISAと学資保険|徹底比較!どっちが自分に合ってる?
ここまでで、
- 「投資で増やす」→ 新NISA
- 「確実に貯める」→ 学資保険
それぞれの特徴が見えてきましたね。
でもいざ選ぶとなると…
「で、結局どっちがいいの…?」
「うちの家庭にはどっちが向いてるのかな…?」
と迷ってしまう方も多いと思います。
そこでこの章では、新NISAと学資保険をズバッと比較!
わかりやすい表と一緒に、それぞれが向いているタイプを整理してみましょう。
● 比較表:新NISA vs 学資保険
| 比較項目 | 新NISA(親名義) | 学資保険 |
|---|---|---|
| 元本保証 | なし(※運用成績次第) | あり(満期まで支払えば確実に受け取れる) |
| 返戻率/運用リターン | 年3〜5%も期待できる(インデックス投資など) | 約105〜110%程度(控えめ) |
| インフレ対策 | ◎ 強い(物価上昇時にも強い) | △ 弱い(固定金額のため目減りの可能性) |
| 流動性(引き出し自由度) | ◎ いつでも売却&用途変更OK | △ 固定されたタイミングでのみ受取/途中解約で損失の可能性あり |
| 保険機能(親の万一時) | × なし(別途生命保険が必要) | ◎ 保険料免除+満期金受け取りなどの保障あり |
| 節税効果 | 運用益がすべて非課税 | 保険料が生命保険料控除の対象 |
| 手間・管理 | やや手間あり(商品の選定・リスク管理など) | 手間少なめ(契約後はほぼ放置でOK) |
| 向いている人 | 資産も育てたい人/投資に興味がある人 | 絶対に元本割れしたくない人/貯金が苦手な人 |
● 結論:「どっちが正解」じゃなくて「どっちが合ってるか」が大事!
ここが大事なポイントなのですが、
新NISAと学資保険、どちらが“正解”ということはありません。
家庭によって考え方や状況が違うからこそ、
- 「少しでも資産を育てたい」なら新NISA
- 「確実に必要額を貯めたい」なら学資保険
というように、目的や性格に合わせて選ぶことがとっても大切なんです。
● 実は…併用もアリ!
迷ってしまう場合や、「どっちも良さそう」と感じた方には…
学資保険+新NISAの“いいとこ取り”作戦もおすすめです!
たとえば、
- 最低限必要な金額(入学金など)を学資保険で準備
- プラスαで必要な費用(通学費・留学・塾など)を新NISAで増やす
という風に使い分ければ、
安心感と柔軟性の両方を確保することができます。
● まとめ:今の自分に合った選び方を
- 「投資初心者だけどチャレンジしたい」→ 新NISAから少額ではじめてみるのも◎
- 「家計にムリなく確実に貯めたい」→ 学資保険を使って強制的に積み立てるのもアリ
- 「どちらかだけに偏るのが不安」→ 併用してリスク分散!
どれを選んでも、早めに準備を始めることがいちばん大事です。
次の章では、「じゃあ具体的にどんな人がどちらに向いてるの?」をタイプ別にわかりやすくご紹介していきます!
7. 自分に合った選び方を見つけよう|新NISAと学資保険の向き・不向き
ここまで、新NISAと学資保険の特徴や違いをじっくり見てきました。
でも、いざ選ぶとなると…
「うちの場合、どっちが合ってるんだろう?」
「投資って気になるけど、実際どうなのかな…」
と迷ってしまう方も多いと思います。
この章では、それぞれの制度が「どんな人に向いているか」をタイプ別にご紹介。
さらに、「迷ったら併用もアリ!」な理由もお伝えしますね。
● 学資保険が向いている人はこんな方!
- 「絶対に元本割れしたくない」安心派さん
- コツコツ貯金が苦手だけど、強制的に貯めたい人
- 保険機能(親に万が一があった場合)も重視したい人
- 節税(生命保険料控除)もちょっと気になる人
- 「子どもの学費だけはしっかり確保したい」と考える方
学資保険は、まさに「堅実&安心型」。
計画通りに貯められる安心感が一番の強みです!
● 新NISAが向いている人はこんな方!
- 資産を育てながら教育費も準備したい人
- 将来の物価上昇(インフレ)がちょっと不安な人
- 少額から投資にチャレンジしてみたい人
- 自由に資金を使えるようにしておきたい人
- 子どもが小さく、運用できる時間にゆとりがある人
新NISAは「育てて備える型」。
リターンは読めない部分もあるけれど、長期で運用すれば銀行預金より大きく育つ可能性も。
● どっちも捨てがたい…そんな方は「併用」でバランスよく!
じつは、最近では “学資保険+新NISA”の併用プラン を選ぶご家庭も増えています。
たとえば、
- 大学の入学金など確実に必要な分を学資保険で準備
- 入学後の生活費や留学費用など不確定な分を新NISAで運用
という組み合わせなら、
安心感と資産の成長、どちらもバランスよくカバーできます。
どちらかひとつに決めきれない…という方は、無理のない範囲で併用を考えてみるのも◎ですよ。
次の章では、おすすめの証券会社や学資保険の資料請求先などもご紹介します。
「ちょっと調べてみようかな」と思った方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
8. 教育資金づくりにおすすめの証券会社・保険会社は?
ここまで読んでくださったママ・パパのみなさん、おつかれさまでした!
最後に、「実際に始めてみたい!」と思った方向けに、新NISAを始めやすい証券会社や、人気の学資保険をご紹介します。
資料請求や口座開設は、無料&ネットでかんたんにできるところが多いので、
「まずはどんなものか見てみたい」という気持ちで気軽にチェックしてみてくださいね。
● 新NISAにおすすめの証券会社【安心・使いやすい3社】
| 証券会社名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 取扱商品がとても豊富。ポイント投資にも対応。 | 初心者〜中級者まで幅広く人気! |
| 楽天証券 | 楽天ポイントが貯まる&使える。使いやすい画面が好評。 | 楽天経済圏の方や投資初心者に◎ |
| マネックス証券 | アプリが見やすく、つみたて設定がしやすい。 | コツコツ投資派の方にぴったり |
選び方のコツ:
・日頃使っているサービスと相性が良いか(楽天なら楽天証券、など)
・使いやすさやサポート体制もチェック!
公式サイトでは、初心者向けの解説ページも充実しているので、
「投資はじめてで不安…」という方も安心してスタートできますよ。
● 人気の学資保険【安定&安心の定番3社】
| 保険会社名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ソニー生命 | 自由度が高く、プランのカスタマイズがしやすい | 自分のペースで計画的に貯めたい方に |
| 明治安田生命(つみたて学資) | 高めの返戻率と安心の保障内容が人気 | 元本保証重視の方に◎ |
| フコク生命(みらいのつばさ) | 兄弟割引あり/祝い金型 or 一括型が選べる | 複数の子どもがいるご家庭にもおすすめ |
※各社とも無料で資料請求できます。
パンフレットを見ながら比較すると「どれが合ってるか」がより明確になります!
● まずは「ちょっと見てみる」でもOK!
- いきなり申し込むのは不安…
- 本当にうちに合ってるか分からない…
そんな方は、まずは資料請求やシミュレーションだけでも十分です。
「うちはどれくらい貯める必要があるのか?」を確認するだけでも、
将来の不安が少しずつクリアになっていきますよ。
● 最後にひとこと:小さな一歩が未来の安心につながる
教育資金の準備って、
「やらなきゃ」と思いながらもつい後回しにしがちですよね。
でも、ほんの少しでも調べてみたり、動き始めたりすることで、
未来の自分にとって大きな安心感になります。
今回ご紹介した制度やサービスも、なにかのヒントになれば嬉しいです。
「やってみようかな」と思ったその気持ちを大切に、
あなたのペースで、無理なく準備を進めてみてくださいね!