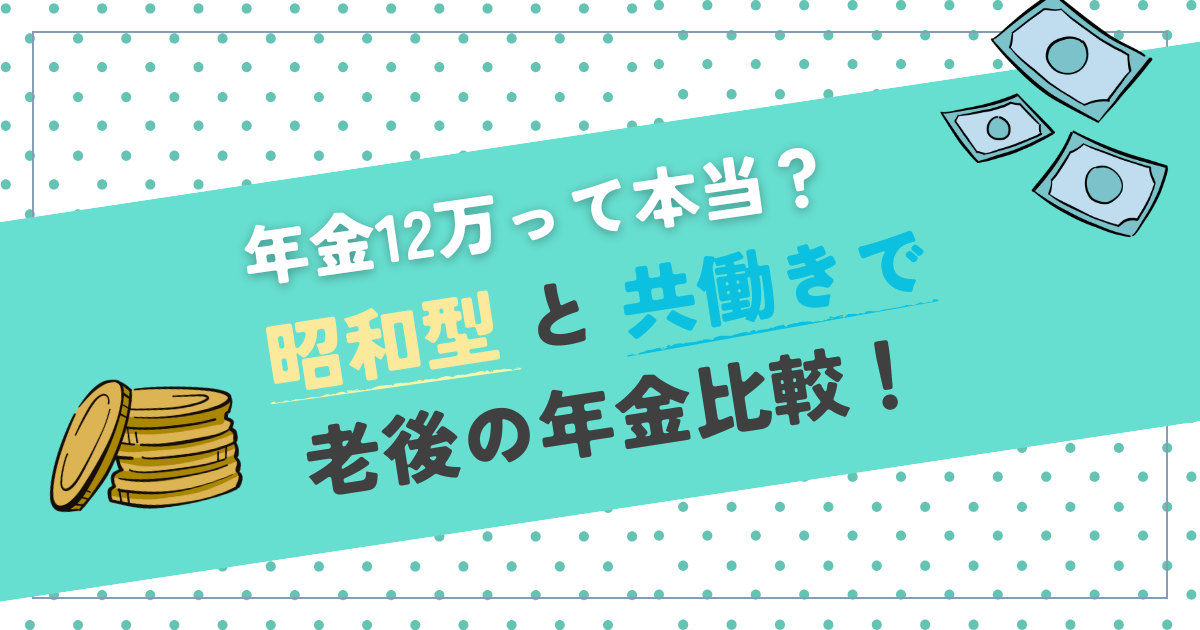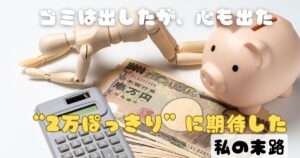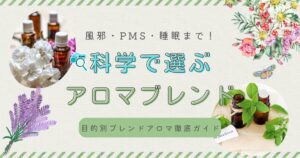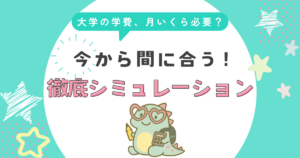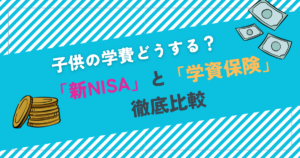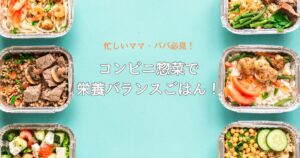「年金12万円って、少なすぎない?」
SNSでもよく見かけるこの話題。でも…それって本当に“うちの場合”にも当てはまる?
実はこの「月12万円」は“平均”にすぎなくて、働き方や家族構成によってもちろん大きく変わります!
今回は、日本に多かった昭和スタイルの「夫会社員・妻専業主婦」と、
最近増えてきた「共働き夫婦(妻も厚生年金加入)」を比較しながら、
老後にもらえる年金と、生活のリアル、そして老後に備え今やれることを具体的にお伝えします!
第1章:まずは「年金12万円」の正体を暴く!
「年金って平均12万円くらいっていうけど、それで生活できるの…?」
そんな不安、きっと一度は聞いたことあるし、感じたこともある人が多いんじゃないでしょうか。
でもちょっと待って!
この“12万円”という金額、実はあくまで【全体の平均】なんです。
つまり──
- 国民年金しか加入していなかった人
- パートや非正規で年金加入期間が短かった人
- 年金を満額もらえる年数に達していない人 ……など、
年金が少なくなる条件が揃った人たちも含めた数字なんですね
たとえば、自営業で一度も厚生年金に加入しなかった人の年金額は、月6〜7万円ほど。
このような人たちも全体の統計に入っているため、全体の“平均”としては12万円という数字になるわけです。
◆ じゃあ会社員や公務員だった人はどうなの?
安心してください。
会社勤めで厚生年金にずっと加入していた人は、実際のところ【月17〜18万円】程度の年金が見込まれることが多いです。
そこに、奥さんの年金が加われば…
- 専業主婦の場合 → +約6.5〜8万円
- 共働きで厚生年金加入あり → +約9〜10万円
と、世帯全体の年金額で見ると月24〜28万円くらいのケースが主流になってきます。
平均に惑わされず、「うちはどうか?」で考えることが大切!
つまり、「年金12万円」と聞いて落ち込む必要はなし!
大事なのは、自分やパートナーの働き方・加入履歴がどうだったかを知ることです。
このあと紹介する「昭和型夫婦」と「共働き夫婦」、それぞれのモデルケースを見ると、「うちの場合だとどうなるかな?」って想像しやすくなるはず。
第2章:昭和型夫婦ってこんな感じ!
昔ながらの夫婦スタイルといえば、
「夫は正社員で定年まで勤務、妻は専業主婦または扶養内のパート」──いわゆる“昭和型夫婦”です。
このケース、今のシニア世代に非常に多いパターンで、実際の年金額も比較的読みやすいのが特徴です。
◆ 昭和型夫婦のモデルケース
| 項目 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|
| 働き方 | 正社員 | 専業主婦または扶養パート |
| 年収 | 約500〜600万円 | ほぼなし(扶養範囲) |
| 年金加入歴 | 厚生年金40年 | 国民年金(第3号)40年 |
◆ 想定される年金額(ざっくり)
- 夫の年金:月 約17〜18万円(厚生年金+基礎年金)
- 妻の年金:月 約6.5〜8万円(国民年金のみ)
→ 世帯合計:月 約24〜26万円
◆ ポイント:扶養でも年金はもらえる
妻が専業主婦やパートで働いていた場合でも、
夫の扶養に入っていれば「第3号被保険者」として自動で国民年金に加入扱いとなっています。
そのため保険料の支払いがなくても、40年分しっかり加入していれば満額(約8万円)の年金がもらえる仕組みです。
次章では、最近増えてきた「共働き夫婦」の年金額を見てみましょう!
収入は増えるけど、その分どう違ってくる…?
第3章:共働き夫婦はどう違う?
最近は共働き世帯が主流になりつつあります。
特に、妻も正社員やフルタイム勤務で厚生年金に加入していたケースは、老後の年金額にも大きく影響してきます。
◆ 共働き夫婦のモデルケース
| 項目 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|
| 働き方 | 正社員 | 正社員またはフルタイム |
| 年収 | 約500〜600万円 | 約300〜400万円 |
| 年金加入歴 | 厚生年金40年 | 厚生年金30〜35年程度 |
◆ 想定される年金額(ざっくり)
- 夫の年金:月 約17〜18万円
- 妻の年金:月 約9〜10万円(厚生年金+基礎年金)
→ 世帯合計:月 約26〜28万円
ポイント:厚生年金があると年金額は大きく増える
妻が厚生年金に加入していた年数が長ければ長いほど、基礎年金に上乗せされる分が増えるため、
年金額が専業主婦モデルと比べて月2〜3万円以上アップすることも。
◆ とはいえ、手取りに差が出ることも
共働き世帯は年金額は多くなりますが、
その分、税金・社会保険料が夫婦それぞれにかかるため、
「年金額は多くても、手取りの差は意外と小さめ」ということもあります。
次は、いよいよこの「月2〜3万円の差」が老後生活にどれほど影響するのかを見ていきます!
第4章:月2〜3万円の差…実はめちゃ大きい?
一見すると、昭和型夫婦と共働き夫婦の年金差は「月に2〜3万円程度」。
「そこまで大きな差じゃないのでは?」と思いがちですが、老後の生活ではこの差がじわじわ効いてきます。
◆ 月々の年金額に差があると、10年でこんなにも差が出る!
年間で24〜36万円、10年で240〜360万円の差!
単純に10年生活すると…
- 月2万円の差がある場合、10年での合計差は約240万円
- 月3万円の差になると、10年での差額はなんと約360万円
これだけの差があれば、
- 家の修繕
- 旅行・趣味
- 孫へのお祝い
- 医療費・介護費用
などの“ゆとり支出”に回せるお金が全然変わってきます。
◆ 老後の生活感にも差が出る
| 内容 | 昭和型夫婦 | 共働き夫婦 |
|---|---|---|
| 基本生活費 | ほぼカバー可 | 余裕あり |
| 趣味・旅行 | 頻度に制限あり | 継続しやすい |
| 医療・介護費 | 出費が増えると不安 | ある程度備えやすい |
| 子や孫への支援 | 控えめ | 比較的ゆとりあり |
◆ 老後資金に余裕があるほど「選べること」が増える
- 「もう少し広い家に引っ越したい」
- 「2年に1回は温泉旅行に行きたい」
- 「子どもの住宅購入時にちょっと援助したい」
こういった“選択肢の多さ”は、年金収入にゆとりがあるほど広がります。
この差を埋めるにはどうする?──
次章では、「年金だけじゃない!老後生活の明暗を分ける“家と固定費”」について見ていきます!
第5章:年金だけじゃない、「住まいのコスト」が明暗を分ける!
年金がいくらもらえるかも大事ですが、
実はそれと同じくらい大切なのが──「毎月いくら出ていくか」、つまり固定費です。
なかでも一番大きな差になるのが「住まいのコスト」、つまり家賃 or 持ち家かどうかです。
◆ 家賃ありの老後は、年金で赤字も…
都心での賃貸暮らしや、老後に新たに部屋を借りる場合、
ワンルームでも月6〜8万円の家賃がかかります。
2LDK以上なら月10万円〜12万円の家賃。
| 家賃 | 年間支出 | 10年での合計 |
|---|---|---|
| 月6.5万円 | 約78万円 | 約780万円 |
→ 都心部で暮らす場合、世帯年金が月24万円あっても、残りで生活費をやりくりするのは少し厳しめ
→ 医療費・介護費などが増えたら赤字に転落する可能性も
◆ 持ち家なら家賃ゼロ=「ゆとりが生まれる」
一方、持ち家なら家賃の支払いはありません。
固定資産税や修繕積立を見ても、月1万円〜1.5万円程度のコストで済むことがほとんどです。
→ 毎月5〜6万円の差が出る
→ 「同じ年金額でも、持ち家の人のほうが圧倒的に余裕がある」
◆ 実は家の有無が“老後格差”を生む最大の要因かも?
| 項目 | 家賃あり | 持ち家あり |
|---|---|---|
| 年金に対するゆとり | 少ない | 大きい |
| 老後の安心感 | 常に不安定 | 安定しやすい |
| 老後10年の住居コスト | 約780万円 | 約120〜180万円 |
年金収入が同じでも、「家を持っているかどうか」で生活の質がここまで変わってきます。
次はいよいよラスト!
今からできる老後の備えを、簡単にまとめていきます!
第6章:今できる対策はある?ある!
ここまで読んで、「うちの年金って実際どのくらいなんだろう?」と思った人もいるかもしれません。
でも安心してください。今からできる備え、ちゃんとあります!
◆ ① まずは「自分の年金見える化」から!
年金は“もらうもの”だけど、どれくらいもらえるかを自分で把握しておくのが第一歩。
- 「ねんきんネット」に登録すれば、将来の年金見込み額がすぐわかる
- 50代の人は「ねんきん定期便(ハガキ)」でも大体の額がわかる
→ 家族単位でシミュレーションすると、かなり現実味が湧く!
◆ ② iDeCoや新NISAで「プチ年金」を作る
「年金だけじゃちょっと不安かも…」という人には、積立型の資産形成がおすすめ。
- iDeCoは老後の受け取り専用で、節税効果も大きい
- 新NISAは自由度が高く、運用益が非課税になる
◆ たとえば:iDeCoで月2万円積み立てた場合…
- 積立額:月2万円 × 12ヶ月 × 30年 = 720万円
- 仮に年利3%で運用できた場合 → 約1,150万円に!
もし運用利回りがもっと控えめ(2%)でも、
→ 約980万円くらいにはなる見込み!
→ 月1〜2万円でも積み立てておくと、10〜20年後には大きな安心材料に!
つまり…
年金にプラスして「+月3〜4万円分の受け取り」にもできる可能性がある!
→ これだけあれば、老後の生活にかなりゆとりが出るよね!
もっと詳しく知りたい人用
◆ iDeCoでどれくらい増やせる?ざっくり試算してみると…
たとえば、iDeCoで月2万円を30年間積み立てた場合──
- 積立総額は:720万円
- 仮に年利3%で運用できたとすると… → 約1,150万円に成長!
もう少し控えめに見積もって、年利2%でも約980万円。
つまり、年金に加えて“プチ年金”のように、月3〜4万円の上乗せができる可能性もあるんです。
◆ さらに、iDeCoは“非課税”ってどういうこと?
実はiDeCoのメリットは「積み立てるだけじゃない」んです。
iDeCoは運用して増えたお金(=運用益)にも税金がかかりません。
たとえば通常の投資だと…
- 運用で100万円の利益が出ると、約20万円が税金で引かれて → 手元には約80万円だけ残ります。
でも、iDeCoなら…
- 運用益がまるごと非課税! → 100万円の利益が出たら、100万円ぜんぶ受け取れる!
この「運用益非課税」という仕組みは、長期で積み立てる人ほど超強力。
普通に投資していたら引かれていた数十万円分の税金が、将来の自分の年金としてそのまま残せるって考えると…すごい!!(もちろん運用リスクはありますがそれを差し引いてもすごい)
◆ 掛金は“全額”が所得控除に!税金がぐっと軽くなる!
さらに、iDeCo最大の強みのひとつが
「毎月の掛金が“そのまま”所得控除になる」という点。
つまり、iDeCoに積み立てた分だけ、自分の課税対象額が減る=税金が安くなるというしくみなんです!
たとえば…
- 月2.7万円(年間32.4万円)をiDeCoで積み立てている人なら
- 年収や税率にもよりますが、年間約5万円〜6万円の節税効果が期待できます!
この節税分だけでも、iDeCoを続けるだけで“将来のお金が増える”+“今の税金も減る”というWの効果。
さらにさっき紹介した「運用益も非課税」なので、
iDeCoはまさに税金面の優等生&未来への貯金箱なんです!
例:月2万円 iDeCoで積み立てると、年間24万円の掛金
その24万円が「全額所得控除」される
年収500万円くらいの人だと、所得税+住民税あわせて約15%が軽減 → 24万円 × 約15% = 約3.6万円の節税効果!
◆ ③ “支出を減らす備え”も立派な対策
・持ち家を早めに完済 or 終の住まいを決めておく
・医療・介護に備えて健康管理を習慣に
・固定費(通信・サブスクなど)の見直しも◎
→ 「入るお金」だけでなく、「出ていくお金」にも目を向けることが大切!
◆ ④ 最後に大事なこと
老後の生活って、年金の額や貯金だけじゃなくて、“今の積み重ね”で大きく変わっていきます。
- どんな働き方を選ぶか
- どこに住むか
- 誰とどんな時間を過ごしたいか
そういうことも含めて、「うちにとってのベストな老後ってどんな形かな?」と考えるきっかけになればうれしいです。
まとめ|「うちはどっち型?」を知ることから始めよう
昭和型夫婦と共働き夫婦、どちらもそれぞれの働き方の中で
しっかり年金を積み上げてきた結果、それなりの生活基盤はできている。
でも、月2〜3万円の差や、家賃の有無、備えの有無が「老後の自由度」に大きく関わるのもまた事実。
まずは、もらえる額を知る
→ 足りない分を補う
→ 固定費を抑える
この3つを押さえておけば、未来はもっと「選べる老後」に変えられるはずです!