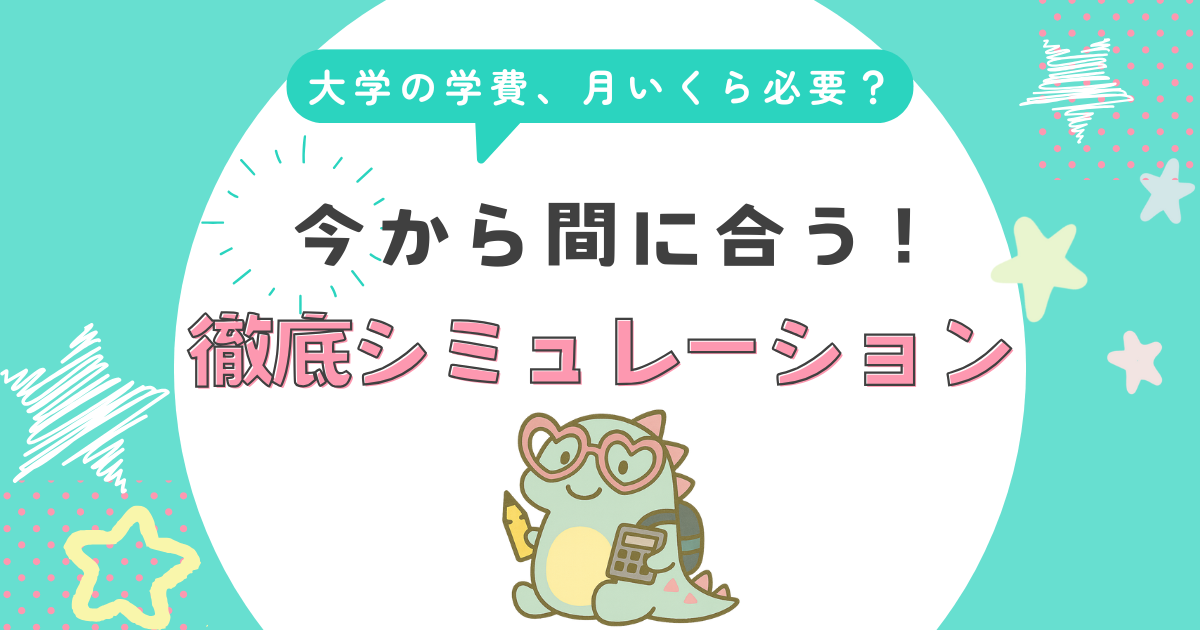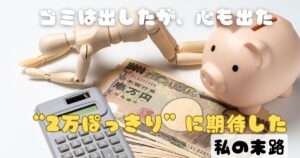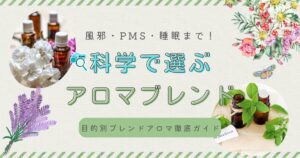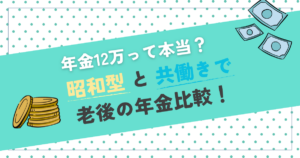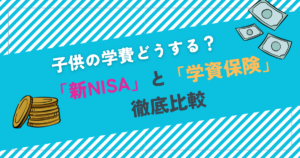1. 「大学の学費って、実際いくらかかるの?」
「教育資金は早めに準備を」とよく言われますが、
中でも特に大きな出費になるのが「大学進学時」ですよね。
でも実際のところ、
「大学って、どれくらいお金がかかるの?」
「その費用を貯めるには、月いくらくらい必要なの?」
「新NISAや学資保険で準備するなら、どっちがいいの?」
…というように、金額の目安がピンと来ていないママ・パパも多いのではないでしょうか?
実は、大学進学にはこんなにかかる!
国公立・私立・理系・文系など、進学先によって金額は大きく変わりますが、
ざっくりとした目安でも400万〜800万円以上の教育費が必要になることもあります。
この出費を、入学直前の数年でまかなうのはなかなか大変…。
この記事では「大学費用×毎月の積立額」が見えてくる!
本記事では、大学進学にかかる学費の平均額(2025年最新)と、
それを準備するために必要な毎月の積立額をシミュレーションしながらご紹介します。
- 国公立/私立文系/私立理系、それぞれの進学パターン別
- 0歳から18年かけて貯める場合
- 5歳から13年でスタートする場合
- 「新NISA」と「学資保険」で準備したときの違い
など、具体的な数字で比較しながら、
わが家に合った資金計画のヒントをお届けしていきます。
「まだ小さいから大丈夫かな…」と思っていた方も、
この記事を読めば「うちの子の未来に向けて、そろそろ準備しておこうかな」と思えるかもしれません。
難しい言葉は使わず、わかりやすくまとめていますので、ぜひリラックスして読み進めてみてくださいね!
2. 大学の学費、最新データまとめ(2025年版)
大学進学にかかる費用は、「国公立」「私立文系」「私立理系」など進学先によって大きく異なります。
ここでは、文部科学省の最新データをもとに、学費(授業料+入学金)のみをわかりやすく比較してみましょう。
● 大学4年間の学費比較表(授業料+入学金)
| 進学パターン | 入学金 | 授業料4年分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 28.2万円 | 214.3万円 | 242.5万円 |
| 私立文系大学 | 25.9万円 | 372.0万円 | 397.9万円 |
| 私立理系大学 | 26.0万円 | 515.9万円 | 541.9万円 |
※この金額は、大学に支払う「入学金+授業料」のみの合計です。
教材費・交通費・生活費などは含まれていません。
- 国公立大学:約242万円
- 私立文系大学:約398万円
- 私立理系大学:約542万円
私立理系は学費がかなり高めですね。
これに加えて生活費(特に自宅外通学の場合)もかかるため、教育費としてはさらに多く見積もる必要があります。
3. 0歳から準備スタート!大学費用の月額シミュレーション(18年間)
では、実際に大学の学費を0歳から18年間で準備する場合、
「新NISA」「学資保険」それぞれで月いくら積み立てる必要があるのかをシミュレーションしてみましょう。
● 前提条件
・ 進学費用は入学金+授業料のみ(生活費は含まず)
・ 新NISA:年利4%で運用できた場合の想定
・ 新NISA:年利4%で運用できた場合の想定
● 結果はこちら!
| 進学パターン | 学資保険(月額) | 新NISA(月額) | 差額(月額) |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 約10,500円 | 約7,700円 | 約2,800円安く! |
| 私立文系大学 | 約17,200円 | 約12,600円 | 約4,600円安く! |
| 私立理系大学 | 約23,400円 | 約17,200円 | 約6,300円安く! |
※この結果は「年利4%」で運用できた場合の想定です。
市場の動向によって実際の成果は変動しますが、インデックス投資などで長期的に平均3〜5%の運用が現実的とされています。
ポイント解説
- 同じ18年間でも、新NISAで運用できた場合は、学資保険よりも月々の負担がかなり少なくなる結果に!
- 私立理系になると、月額で6,000円以上の差が出る可能性も。18年間で考えると100万円以上の差に!
4. 今からでも間に合う?5歳スタートでの積立シミュレーション(13年間)
「うちの子はもう5歳だから、今さら学資保険やNISAを始めるのは遅いかも…?」
そんなふうに思っているママ・パパも多いかもしれません。
でも大丈夫!5歳スタートでもしっかり準備できます。
ただし、月々の負担は少し重くなるので、そのあたりも含めて見ていきましょう。
⚫️前提条件
・準備期間は「5歳〜18歳までの13年間」
・学資保険:返戻率107%
・学資保険:返戻率107%
● シミュレーション結果はこちら!
| 進学パターン | 学資保険(月額) | 新NISA(月額) | 差額(月額) |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 約14,500円 | 約11,900円 | 約2,600円安く! |
| 私立文系大学 | 約23,800円 | 約19,500円 | 約4,300円安く! |
| 私立理系大学 | 約32,500円 | 約26,500円 | 約5,900円安く! |
● ポイント解説
- 準備期間が5年短くなるだけで、月額は約1.5倍に!
- 新NISAでの運用益が出れば、月5,000円〜6,000円ほど節約できる可能性もあります。
新NISAは「親名義で積立て→将来子どもに使う」形になるため、柔軟性が高く、年齢制限もありません。
※5歳以降から学資保険に加入する場合、一部プランは加入対象外となることがあります。
5. いつ始める?開始年齢でこんなに違う!月額の比較
ここでは、「教育費の積立って早く始めた方がいい」とよく言われる理由を、
年齢別のシミュレーションで見ていきましょう。
0歳・5歳・10歳の3つのタイミングで積立を始めた場合、同じ進学費用でも毎月の負担は大きく変わります。
● 比較前提
- 積立期間:0歳(18年間)・5歳(13年間)・10歳(8年間)
- 進学費用:授業料+入学金のみ
- 新NISA:年利4%で運用できた場合
- 学資保険:返戻率107%想定
● 年齢別の月額比較(進学パターン別)
| 進学パターン | スタート年齢 | 新NISA(月額) | 学資保険(月額) |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 0歳 | 約7,700円 | 約10,500円 |
| 国公立大学 | 5歳 | 約11,900円 | 約14,500円 |
| 国公立大学 | 10歳 | 約21,500円 | 約23,600円 |
| 私立文系大学 | 0歳 | 約12,600円 | 約17,200円 |
| 私立文系大学 | 5歳 | 約19,500円 | 約23,800円 |
| 私立文系大学 | 10歳 | 約35,300円 | 約38,400円 |
| 私立理系大学 | 0歳 | 約17,200円 | 約23,400円 |
| 私立理系大学 | 5歳 | 約26,500円 | 約32,500円 |
| 私立理系大学 | 10歳 | 約47,900円 | 約51,100円 |
※新NISAは年利4%、学資保険は返戻率107%でシミュレーションした目安額です。実際の契約内容や運用成績により異なる場合があります。
● ポイント解説
- 0歳スタートなら月1万円前後でOKだった積立も、10歳スタートでは月2万円以上に!
- 新NISAを活用できた場合は、学資保険よりも月々の負担が少なくなる可能性が高い
- 早く始めるほど、少ない金額で大きな教育資金が準備できる
6. まとめ|教育資金は“いつ・どうやって”準備する?
ここまで、大学の学費がどれくらいかかるのか、そしてそれを新NISAや学資保険で準備した場合に、
毎月どのくらい積み立てれば良いか?を具体的に見てきました。
● あらためて確認!学費の目安と積立の違い
| 進学パターン | 4年間の学費(授業料+入学金) |
|---|---|
| 国公立大学 | 約242万円 |
| 私立文系大学 | 約398万円 |
| 私立理系大学 | 約542万円 |
そして、積立額は次のように変わってきました
0歳スタートなら月1〜2万円台
5歳スタートなら月1.5〜2.5万円台
10歳スタートなら月2〜3万円台以上に!
● 新NISA or 学資保険、メリットデメリット表比較
| 比較項目 | 新NISA | 学資保険 |
|---|---|---|
| リターン(増える可能性) | ◎ 年3〜5%も狙える | △ 控えめ(105〜110%程度) |
| リスク | △ 市場によって変動 | ◎ 元本保証がある安心感 |
| 柔軟性 | ◎ いつでも引き出せる | △ 解約時に元本割れのリスクも |
| 万一のときの保障 | × なし(別途保険が必要) | ◎ 保険料免除&満額支給など |
| 税制面の優遇 | ◎ 運用益が非課税 | ○ 保険料控除あり |
● 結論:「自分たちの性格や目的に合わせて選ぼう」
「少しでも資産を増やしたい」「柔軟に使いたい」→ 新NISA向き
「元本割れしたくない」「安心重視で貯めたい」→ 学資保険向き
「どちらもメリットがある」→ 併用もアリ!
そして何より大切なのは…
“できるだけ早くスタートすること!”
同じ目標でも、準備期間が長いほど月々の負担はぐっと軽くなります。
まずはシミュレーションして「うちの場合はどうかな?」と考えるところからでもOKです◎
次にやってみたいこと
- 自分の子どもが「何歳で」「どのくらいの学費がかかりそうか」を調べてみる
- 新NISAや学資保険の資料を請求して、内容を比較してみる
- 家計の中で「毎月どれくらいなら積み立てできそうか?」を考えてみる
未来の教育資金は、「いつか」じゃなく、「今」からの少しずつでしっかり準備できます。
この記事が、あなたとご家族の安心の第一歩につながればうれしいです!
下記記事に、それぞれの制度の違いや向き・不向きを詳しくまとめています。
迷っている方は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね!